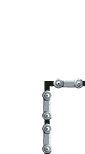 |
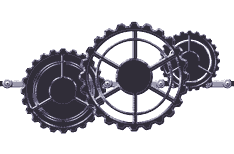 |
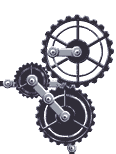 |
「…………遅い」 『坊ちゃん、そうカリカリしなくても』 誰よりも早くモンスターを倒したリオンは扉の前で待っていた。他の者はまだ戻ってきていない。 シャルティエの言葉に溜息を吐くと、リオンは仕掛けを見る。三つ目が割れたところだから、恐らくもうすぐ誰かが帰ってくるだろう。 「……………………シャル」 『何ですか? 坊ちゃん』 「、と言ったか。あいつは……似ているな」 『…………』 シャルティエは誰に、と聞き返さなかった。 リオンの小さい頃から傍らにいた彼は、その想い出も殆ど共有している。それ故にリオンが誰のことを言ったのか、すぐに理解していた。 『でも案外本人とか?』 「あいつは男だろう。……彼女は女だ」 『…………』 再びシャルティエが沈黙する。 珍しいことだなと思いながら壁に背を預けていると、ルーティとマリーが戻ってくる。 「あら、もう終わってたの?」 「遅い。時間を掛けすぎだ」 ムスッとして返すリオンにルーティが言い返そうとした瞬間、仕掛けの四つ目が割れる。 それを見て、どちらが先に倒したのだろう、とマリーが呟く。 やがてやって来たのはスタンだった。 「悪い悪い。結構手間取っちゃって」 『全く、力任せに向かっていくからだぞ』 「悪かったって」 スタンとディムロスの遣り取りを聞きながら、最後の仕掛けの解除を待つ。だが、待てど暮らせど仕掛けは解除されない。 仕方ない、とリオンが壁から背を離した時、 《うわーん!!》 頭の芯に響くような大声が、どこからともなく聞こえてきた。 「何だ、今の声は」 「……あっちはが行った方よね?」 「行ってみよう!」 マリー、ルーティ、スタンがそう言うと、頷きあって走り出す。リオンもすぐその後に続いたが、声の聞こえ方に疑問を持っていた。 頭に直接訴えかけるような、声。まるでソーディアンのような。けれど、マリーにも聞こえていると言うことは、そうではないと言うこと。 一体何なんだと思いながら、リオンは廊下を走る。 《死なないで、死んじゃ駄目だよーっ!》 声はなおも響いている。そのお陰で部屋を見つけるのは容易だった。 開いていた扉から中に入ると、扉の真正面の壁際でぐったりしたまま動かないと、そこからだいぶ離れたところに落ちているの剣が視界に入った。 リザードマンの姿は、ない。だがレンズも落ちていない。 「みんな! 上だ!」 マリーの言葉の一拍後、リザードマンが上の方から降ってきた。 間一髪避けると、その尻尾で薙いでくる。恐らくはそれにやられたのだろう。それも避けると、漸く反撃に転じることが出来た。 まずリザードマンを倒し、それから石のようなモンスターも倒す。そうやって危険を除いてから全員での方へ寄っていった。 《うわーん、どうしよう、私の所為だ! 死んだら、が死んだらどうしよう!》 声が延々と嘆いている。延々延々延々…………。 「…………五月蠅い少しは静かにしろ」 怒気を孕んだリオンの言葉に、漸く声が収まる。と、思えば次の瞬間には明るい声を出した。 《アトワイト! そうよ、アトワイトさんに直して貰えば……》 「………………………………その字じゃナイし」 声に突っ込みを入れつつ、はふぅ、と息を吐き出した。 その動作だけでも痛むのだろうか、眉を寄せて表情を厳しくする。 「とりあえず喋るにしろ動くにしろ、どうにかしなければならないようだな。……おい」 「おいじゃないわよ!……いいわ、治してあげる」 「ありがとう」 に晶術を掛け、ルーティは一息吐く。どうやら打撲だけのようで、それだけですんだのは幸いだった。 そんなの前にスタンが剣を持ってきて、そっと置く。その剣を掻き抱きながらはリオンを見つめる。 「説明は、必要?」 「ああ、もちろんだ」『え、説明するの?』 リオンとシャルティエの声が重なった。 どういう事だと責めるようなリオンの視線がシャルティエに注がれる。 人間だったら冷や汗を流しているだろうシャルティエに苦笑しつつ、とりあえずまだ残った痛みによって立ち上がれない今の自分をどうするかとは頭の隅で考え始めた。 「まず、ぼくのことを心配していた声だけど。……七本目のソーディアンもどき、のようなものだ」 《もどき!? もどき扱い!?》 とりあえず簡潔に話を終えようと思って話し出せばコレだ。……どうしてもちゃんと話させたいらしい。 もちろん、目の前のカトレット姉弟やスタン、マリーも興味津々というか疑惑の目というかを向けてきている。正直言えばぼくはそう言う視線が嫌いだ。いやだって、興味を持たれても誤魔化す立場は辛いのだよ。 溜息を吐き、頭を掻く。 「ぼくはね、千年前の天地戦争時代にちょっとだけいたことがあるんだ」 『ちょっと、と言うより結構入り浸っていたわよね?』 「アトワイト、突っ込まないで欲しいな」 確かキミはぼくの事情を知っていた筈なんだけどね? 言外にそう言うと苦笑する雰囲気が伝わってきた。 「その時に……ハロルドの技術を応用しつつ作ったんだよ」 「千年前にいたことがある、とは?」 黒髪君…………カトレット弟が聞いてくる。そりゃ疑問にも思うだろうね。 「ん、ぼくはこの世界の住人じゃない。異世界を渡る異邦人。故に時代はこちらから指定出来マス」 「へー、凄いんだな」 素直に感心してくれるスタン。うん、こういう反応は好きだね。 ルーティやマリーもさして疑問は持っていないらしい。信じ難そうな表情だけどね。 「だから普通のソーディアンと違うんだよ。そしてぼくの兄の作品だからね、歴史には載ってません」 使えるのはぼくか彼女が認めた相手だけだし。 「ちなみに人格は妹のものなんだ」 《改めて。です、よろしく》 ぴくり、と。 の自己紹介を聞いてカトレット弟の片眉が上がった。まるで……見知った名前を改めて聞いたかのように。 当たり前だと思う。もぼくも、彼とは前に会っている。名前を聞いたこともある。ぼくは名乗ってないけれど。それに、は「普通の人」だったから。 「よろしく、」 「アトワイトは知っていたの? とのこと」 『ええ。私もディムロスも、シャルティエも知っていたわ。ソーディアンチーム全員が知っていて、ハロルドやリトラーも。……あなたを憶えていたわ』 アトワイトの最後の言葉は、ぼくに向けて放たれていた。一瞬、涙が出そうになる。 「どういう事?」 『そのままの意味だ』 スタンの問にディムロスがそう答えると、とりあえず先を急ごうという話の流れになる。まぁそりゃそうだろうね。 を掻き抱いていた手を緩め、ぼくは懐からレンズを一つ取り出す。それを柄の飾りの部分――――――――実際はレンズの力を増幅させる装置なのだけど、どうやって作ったのかは企業秘密なのでぼくも知らない。そこに填め込む。 「キュア」 一言囁くように言って、自分の身体を治す。だって今のカトレット姉じゃあ完璧に治せなくて、背中が酷く痛むんだ。 治ったことを確認して、ぼくはその場から立ち上がる。 痛みもないから完璧だろう。 「さ。行こうか?」 「……打撲だけじゃなかったのか?」 「ん、何がだい?」 鋭いな、カトレット弟。 打撲に見えても身体の中はどうなってるか案外わからないものなんだよね。アトワイトも剣になってしまった今は触診できないわけだし。見た目だけなら誤魔化す自信があるからね。 そんなぼくに近寄って、カトレット弟はぼくの背中を見る。…………打撲だけですが、表面上は。 「何を見てるのかネ?」 「……………………別に」 それだけ言うとぼくに背を向けて歩き出す。部屋から出て行くその背をスタン達が追っていく。……あ、カトレット姉が振り返った。 「ほら、あんたも早く行くわよ!」 どうやらぼく、仲間として彼女に認められたようです。 「ああ、今行くよ」 苦笑しつつ、ぼくはを引きずるようにして一行の後を追った。 後書き |
||
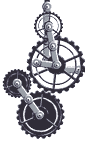 |
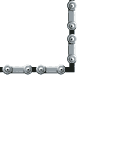 |