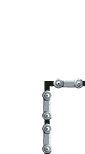 |
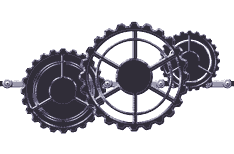 |
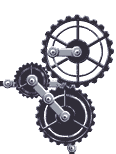 |
そいつに出会ったのは、王によってもたらされた密命によりストレイライズ神殿へ向かったときのことだった。 人の気配がないので扉を開けると、そこにはモンスターの大群が瀕死で床に平伏していた。その真ん中には大剣を持った少女の姿。 否、それを少女と言い切っていいのか。中性的な雰囲気を身に纏うのは、短い蒼髪と身体にフィットした黒の上下――――上はノースリーブで顎下まで襟があり、下は短く膝の少し上で終わっている――――の所為だけではないだろう。胸を覆うように軽い鎧、プロテクターのようなものを付けており、腰には布を巻いて円状の留め具で留めている。もしかしたら、少年かもしれない。 だが、どちらにしろ彼、もしくは彼女がいる場所はその風貌に似合わない。 神殿の中、瀕死のモンスター達に囲まれ、平然とその場で立っている。その手に持つ大剣も不釣り合いだ。 『…………っ』 ソーディアンの、声にならない声が聞こえた気がした。 視線を下げ、自分の持つソーディアンへ向けるが、何も反応はない。兎に角、いつまでもそうしていても仕方ないので、僕は声を掛けることにした。 「貴様、何者だ?」 この言葉に漸く振り返ったその顔が、一瞬歪む。銀の瞳が僕を映し込み、驚きと別の感情が綯い交ぜになったような複雑な色を湛える。 「ん、ぼくのことかい?」 ぼく、と一人称を使った彼、もしくは彼女は首を傾げつつ大剣を背の鞘に仕舞う。先程の揺らぎはもうその瞳に残っていなかった。 「ぼくは遥那と言う旅人さ。……神殿に用があったんだが、この有様でね。何があったやら」 やれやれと肩を竦めるその様子を訝しがりながら、とりあえず周りのモンスターに止めを刺していく。 ちらりと視線をやれば、それを見ていたは飽きたのか、ひょい、と神殿の奥の方を見た。その視線につられ、全員がそちらを向く。 「うん? 向こうの方に人の気配を感じるね」 そう言うとモンスターに注意を向けず、そのまま歩き出す。 一つの扉の前で立ち止まると、その周りの様子を観察していく。斜めから、真正面から、横から。あらゆる角度で。そしてそれを終えると踵を返して別の方向へ行こうとした。 「おい、何処へ行く」 「その扉を開けに。……何カ所かの装置を破壊しないと駄目みたいだからな」 ひらり、と手を振っては歩き始める。まるで神殿の地図があらかじめ頭に入っているかのような軽い足取りで奥へと進んで………… 「うわっ、行き止まってる!?」 ただの考え無しらしい。 そう思うと、僕は後ろのスタン・エルロン、ルーティ・カトレット、マリー・エージェントを少し振り返り、足早にの後を追う。 それを待っていたかのようなタイミングでは袋小路になっている通路から出て来ると、今度は迷いなく一つの部屋の前に来る。 「ここに扉を開ける何かがある」 「根拠は」 「勘」 そんなを疑わしい、とも怪しい、とも思わずにいる自分を不思議に感じながら、それでも部屋の扉を開く。中にはトカゲのような姿形のモンスターと、石のような形の何か。それもモンスターなのかもしれない。 確かに勘は当たっていたようだと呟くと、ソーディアン・シャルティエを鞘から抜き放った。 「行くぞ!」 言って、僕は率先してトカゲのモンスター……リザードマンに斬りかかっていく。 スタンやルーティ、マリーも続くが、はそれを傍観している。 「お前も戦え」 「面倒だね。……おーけぃ、解ったから切っ先を下げてくれないか?」 近くに来た時に即答されたが、シャルの切っ先を首筋に突き付けると、冷や汗混じりに承諾する。 そしては自分の剣を背中の鞘から抜き放った。 刃の根本の部分に丸い石のようなものが埋め込まれた造形。柄の先端の方は二重になっているようで、段差がある。そしてレンズの形を模した透明な飾り。 「面倒だなぁ」 溜息と同時、飾り部分に手を当てる。すぐにその飾りは半分に分かれ、中の空洞を見せる。そこに懐から取り出したレンズを入れると、飾りを元に戻す。 レンズに白い光が灯った。 「離れろ! サンダーブレード!」 目映い閃光と雷の刃がリザードマンを切り裂く。それと共に飾りに入っていたレンズが消失する。 リザードマンに止めを刺したのは、マリーだった。 「晶術が使えるの?」 「一応は。レンズがあれば」 「へーっ、凄いんだな」 の周りに集まるスタンとルーティ。マリーもルーティの斜め後ろで聞いている。 「ああ、後でキミ達全員の名前を聞かせてくれないか」 そう言ってはすぐさま踵を返し部屋を出る。 扉の前に戻ってみると、飾りと思われたものが一つ砕けていた。 「あと四つ同じのがあるみたいだ。……金髪君は一人でいいだろ、女性は纏まった方がいいね。んで黒髪君も一人でいい、と。ぼくはもちろん一人だけど」 「オレはスタンだよ」 「あたしはルーティよ。気遣いありがとう」 「私はマリーだ」 の言葉にそうやって自己紹介していく。ソーディアンは一言も言葉を発しない。普段五月蠅いシャルでさえも、だ。 それじゃあ向こうを、と左側の廊下を指し、スタンとルーティ、マリーを向かわせる。 後ろ姿を見送ってから僕の方を見て、は溜息を吐いた。 「向こう、早く終わるといいけど」 「無理だな」 即答した僕に苦笑し、歩き出す。またしても迷いない歩み。 「お前は、ここを知っているのか?」 「知らない。でも 「…………それはどう違う?」 「知識と、実際は、違う」 そう言って少し歩みを早める。 足早に隣に並び、その顔を横目で見る。銀の瞳は、悲痛に歪められていた。何を思い描いているのか解らない、けれど見ている者に 「ぼくが 再び見た瞳はただ前を向いていた。 暫く歩き、一つの部屋に辿り着く。 「じゃあ黒髪君。キミここね」 そう言っては僕に背を向け、別の部屋へと向かっていった。 後書き |
||
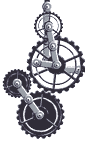 |
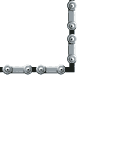 |