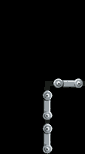 |
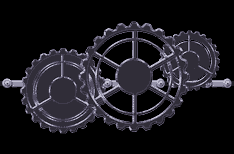 |
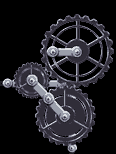 |
開かれた扉の奥には、何もなかった。 「そんな、神の眼がっ」 呆然と呟き、この事態に途方に暮れる神官。その横をすり抜け、破壊された部屋の中を視る。 ふと、の視線が部屋の一カ所で止まった。 「……万能薬、ってあります?」 「パナシーアボトルのこと?」 「多分それです」 「何に使う気だ?」 聞いてきたリオンに、視線を留めたままの石像を指さす。石像というには、おかしな格好。 それで得心いったのか、パナシーアボトルを取り出すとその石像に向かって使う。地球という場所では見られるはずのない現象が起こり、石像が人間の姿を取り戻した。 「…………グレバム様! お止めください!」 どうやら叫んでいる最中に石像にされていたようだ。戻った途端、続きを口にする。そして周りに見知らぬ者が多数いることを認め、その口をすぐに閉ざした。 「グレバムを知っているのか?」 「え、ええ」 リオンの問に状況整理が出来ないまま彼女は頷く。 「そうか。もう一つ聞く。……神の眼は何処だ?」 「ああっ、そうですわ! グレバム様が神の眼をっ」 「持ち去った、とか?」 石像だった女性の言葉を勘で補完しつつ、はリオンの方を見た。 顔を歪ませ、苦虫を噛み潰したような表情をしていた彼は、小さく舌打ちをすると女性に向き直った。 「お前の名は?」 「あ……フィリア・フィリスと申します」 何故今名前を聞く、とスタンやルーティが首を傾げる。とりあえずも便乗して首を傾げてみるが、何となく予想は付いていた。 グレバムの顔を知る者は、恐らくフィリアしかいないだろう。 案の定リオンはそう言い放つと、連れて行って欲しいというフィリアに少し眉を顰めただけで何も言わなかった。 王都・ダリルシェイド。 はリオンに、身元不明人であると同時に今回協力した一般人として王に謁見させると言われてここまで付いてきた。 本来ならば、怪しいとしてすぐに捕まっても何も言えないのだが、出会ったのが物語の中核をなす彼等だ、そうそう悪いことにはならないだろう。そう判断し、尚かつどう足掻いても連れて行かれそうなので黙って付いてきたのである。 リオン、フィリアと共に謁見室へ通され、王にお目通りする。その謁見の最中、は会話に集中できなかった。 自分の処遇や説明に不安はない。リオンに一任しているが、いきなり「異世界からやって来た」等と言うことはないと事前にリオンに言われていた。 場面に直面した自分たちならいざ知らず、他の人間には頭のおかしい人間に思われるだろうから、と一応気を遣ってくれたのだ。 そうして記憶喪失であるという嘘をプラスされた自分のこと、フィリアのことをリオンが簡潔に王へと説明していくのを頭の端で認識しながら、は先ほどから感じる悪寒の元を探していた。 絡み付くような視線。絡み付き、値踏み、そうして全てを手に入れようとするような。背筋が凍り付く視線。 その視線が、の意識を会話から引き離していた。 話も終盤に差し掛かった頃、その元をセインガルド王の傍らに見つける。 ぞっとするほど冷たい瞳で自分を見つめる男。その後ろには……否。それに重なるようにしてもう一人男が立っていた。 怖い、そう思った瞬間。 「、と言ったな」 「っ、はい!」 王に声を掛けられ、弾かれたように顔を上げる。 「記憶喪失だが腕が立つというではないか。今は少しでも神の眼奪還の為の力が欲しい。リオンと共に神の眼を追ってはくれぬか?」 「はい、わかりました」 ほ、と胸の中で息を吐く。ここでもし王があの隣の男の意見を聞き、ここに残ることになったらリオンに縋り付いてでも付いていこうと考えていた。だがそれは杞憂に終わったようだ。 それとも、これもあの男の掌の上の出来事なのだろうか? ぞっとしない考えに僅かに眉を顰め、頭の中から追い出し、今度こそ会話に集中する。 そして王の直々の命により、神の眼奪還チームには組み込まれた。 ぐぅ、と伸びをしつつは港でスタン達が聞き込みを終えるのを待っていた。 リオンはと言うと、一度城から出たもののすぐに何処かへ行ってしまった。何か大切な用事があったのだろう。 鉄柵の上に腰掛けつつ、視線を空へと向ける。 死んだはずの自分。ならここにいるのは霊体か。けれどみんなに見えるし触れられるし。死んだようには思えない。その感覚は普段から境が曖昧だからかもしれないが。 そう思いつつぼぅっと時が過ぎるのを待つ。 青い空が、目に染みた。 あそこで生きる、と決めた、筈なのに。 どうして私は、ここにいる。
「〜!」
スタンの声に現実に思考を現実へ戻すと、手招きをされる。それに頷き、走っていくとカルバレイスへ向かって大きな荷物を載せた船が出たという情報を教えてくれた。 「追わないと、だね」 「だけど、魔の暗礁って所に化け物が出て船が出せないらしいのよ」 「化け物……でも、行くしかないんでしょ?」 「ああ。だから頼み込んでいるんだが、誰も聞いてくれなくてな」 ルーティとマリーと共に眉を寄せつつ打開策を考える。 そんなの耳に溜息が聞こえてきた。 「何をしている」 「あ、リオンさん」 「…………何故お前にまでさん付けされるんだ?」 「何となく」 にこりと笑ってリオンを見ると、呆れたように溜息を吐かれた。 とりあえず情報収集の結果を報告すると、リオンはまた溜息を吐いた。 「また呆れるようなこと、言った?」 「違う。……出来れば使いたくなかったが、オベロン社の船を使う」 オベロン社。レンズを民間から買い取り、それによって作った生活用品を売って成り立つ会社。リオンの上司、ヒューゴ・ジルクリストはオベロン社の総帥。故にこの流れは納得できるものだ。 けれど、はそのヒューゴという人物が恐ろしかった。オベロン社という組織を抱える個人が。 何より、彼に重なるように立っていた金髪の男が。 重なるように立っていたことから、人間でないのは明白で。しかしそれが一体どういう状態なのか、には考えることすら恐ろしく感じられた。 「あ、の。…………王様に必要だから船を貸すように、って命令を出して貰ったら? そうすれば、使わなくてすむと」 ヒューゴの手を借りたくないという一心で提案してみると、暫し顎に手を当ててリオンは考える。 「……そうだな。目立たないようにするにはそれが一番か」 少し考えた後、リオンはあっさりそう言ってマントを翻す。暫くすると王の勅命を持って戻ってきた。 それだけで王の信頼が厚いのが解る。 船はその勅命によってカルバレイス、つまり魔の暗礁へ向かってくれることになった。 その、船の上。 波を割る音と船の揺れと潮風の中、は髪が乱れることも気にせずに甲板に立っていた。 黒瞳は真っ直ぐと海を見つめ、穏やかな色を湛え続ける。 青い色だけが視界を染め上げるその景色を、飽きることなくは見つめ続けていた。 「」 その背中に、ルーティの声が掛かる。 「あんたどうして王の勅命なんて求めたの? オベロン社の船の方が早く調達できたでしょうに」 何処か納得いかなさそうなその声に、苦笑しつつ振り返る。 「うーん、何となく。リオンさん、使いたくなさそうだったし」 「あー、あいつなんて呼び捨てで十分よ」 「……そんなに嫌い?」 「嫌い、って言うか…………生意気」 腕を組んで不機嫌そうに言うルーティにさらに苦笑すると、じろりと見られる。 視線をあからさまに逸らしてから、ふと一点で目を留める。 「…………あ」 「どうしたのよ?」 その様子を訝しく思ったのか、ルーティが怪訝そうに聞いてくる。それに何でもないと返しつつ、は視線を海の方へと移す。 視界に入ったのはリオン。船員に見張りでも言いつけているのか、はたまたただ何かを聞いているのか、船員が彼の側にいる。 少し忙しそうだな、と考え、当たり前か、とも考える。 何時いかなる状況で何かが起こるかもしれない。そうすると、指揮を執るのは客員剣士であるリオンになるのだろう。 そう思っていると、能天気な声が聞こえてきた。 「うわー、ホント凄いなーっ。一面海だよ」 スタンの声に振り向く。 喜色満面な彼の様子に、一瞬だけ犬の尻尾の幻影を見てしまう。 「あんたねー、海なんて珍しいもんじゃないでしょ」 「それでもさ、凄いじゃないか。一面海だなんてさ」 それに俺、山育ちだから海は初めてみたいなもんだし。 そう言ったスタンの横にフィリアが進み出てきた。横に並ぶと、にこりと笑って潮風に遊ばれる髪を手で押さえる。 「そうですわね。とても綺麗ですし」 会話にフィリアも加わってきた。 さらに賑やかになるかと思われたところで、 「お前達、少しは静かにしろ」 リオンがそう言って場を納めた。上のデッキから少し身を乗り出して注意しているところからして、彼にとっては気に障る五月蠅さだったのだろう。 はーい、と何故か参加していなかったが謝り、ルーティに小突かれるというほのぼのとした光景が一部繰り広げられた。 後書き |
||
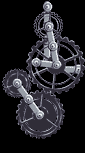 |
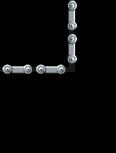 |