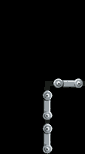 |
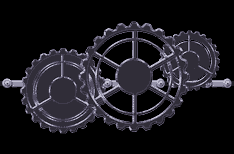 |
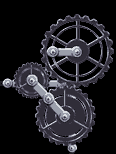 |
彼女の印象は、月だった。 太陽みたいに強い光を放っているわけではない。けれど、ふとした瞬間に目が行ってしまう。そんな、月。 真昼の空に浮かぶ月のように儚い雰囲気も持ちながら、夜に生きる者を優しく見守る雰囲気も持ちながら。 闇を明るく照らして、それでも不快ではないその光は、恐らく何者にも揺らがない。信念と同じような輝きで、それよりもずっと強く。 だからなのだろうか。 闇に生きるモノも光に生きるモノも、彼女の光に心穏やかにされてしまう。彼女の光の側にいたいと願ってしまう。 光に惹かれ、集い集まり、彼女の光を欲する。それは、闇の運命。光はそれを護ろうと彼女の周りに集うだろう。 それ故に過酷な運命を背負い、それでも。 彼女はここに生きていた。 イヤホンを耳に填め、MDを聞きながら長い黒髪の少女は道を歩く。 腰まで届く黒髪を水色のリボンで結わえ、歌に聴き惚れているのか、今は半分程までに細めている他の者よりやや色素の薄い黒瞳は前を見つめている。薄く色付いただけの唇やその白い肌には、化粧の類は一切見受けられない。 リボンにあわせたのか、白い薄手の長袖上着と水色のTシャツ、それに白いロングスカートが清楚、と言った具合である。 少女の名前は。その地域にある高校の一学年だ。 「っ」 後ろから呼ぶ声が聞こえたので、MDを止めては振り返った。 に向かって走ってきたのは、黒い短髪に少々下がり気味な目尻の黒瞳を持つ少年。どうやら学校帰りらしく、制服を着ていた。 彼はの幼馴染みで、私立のエスカレーター式学園に通っている。名前を遥那悠。 の目の前で止まると、悠は少しの間肩で息をして呼吸を整える。それを何も言わずに見守り、落ち着いたところでは話しかけてみた。 「悠君。どうしたの?」 「いや、この前僕、MD借りてプレーヤー壞したでしょう?」 「ああ」 気にしなくてもいいのに、と苦笑すると、カバンの中を漁り出す悠。と、袋に入ったMDプレーヤーを渡してくる。 にこりと笑ってにそれを握らせると、 「知り合いに貰ったんです。丈夫だから簡単には壊れませんよ」 僕の気持ちの整理の為だと思って受け取ってくださいね。 そう念を押され、頷く。 ただ、今自分が持っているMDプレーヤーをどうしようという次の難題がの前に出てきたが。 よかったと安堵すると、悠はの格好に首を傾げる。ラフな格好はどう考えても、これから何か用事があるといった感じだ。 「えっと、邪魔、しました?」 「ううん。ちょっと本屋に行こうと思ってただけ。遠慮しなくていいよ」 少し俯き気味に悠が呟いた言葉に首を振り、は受け取ったプレーヤーを上着のポケットの中へと入れた。 にこり、とどちらともなく微笑むと、二人揃って歩き出す。 「悠君は部活だったの?」 「ええ。と言っても、報告会みたいなものですね」 苦笑しつつ部活内容を反芻する悠を見ながら、は安堵していた。 悠が今の学園に行ったのは中学三年の初め。それまで通っていた中学から親の都合でそちらへ移されたらしい。 その学園で何があったのか知らないが、一時期悠から感情というものが消えていた時期があった。それを無理矢理乗り込んでいって元に戻したのがである。その後のことが気になるのも仕方がない。 経過は良好、等と心理カウンセラーのようなことを考えながら、次の話題へと移る。 「そうだ、悠君。オススメのMD貸してくれないかな」 「持ってるの、聞き飽きました?」 「毎日聞いてたからね」 「じゃあ先刻渡したMDに、遅れた謝罪の分も込めまして」 取り出したMDに「専用」と携帯していたペンで書き、渡してくる。 「いいの?」 「いいの。……その一曲目が一番オススメですよ」 ほにゃんと笑うとペンを仕舞う。 その様子を見て、ふとは呟いた。 「それって何の曲?」 「僕の大好きな曲ですね。ゲーム曲です」 胸を張るようにしてそう言う悠に、だから何の曲だと聞いているのだけれどと眉を顰めてみせる。 その様子に肩を竦め、悠はなんてことはないというように教えてくれる。 「テイルズオブデスティニーの主題歌ですよ。略してTOD」 「略さなくていいです」 呆れながら苦笑して、はそのMDをポケットに仕舞い込む。 そう言えばつい最近、悠が「一番の名作がセリフを殆ど書き直してリメイクされる」と騒いでいたのを思い出した。恐らく、そこまで言わせるほど悠が名作だと思っているものがテイルズオブデスティニーなのだろう。 昔散々それについて語られたこともある。それの続編は最近プレイしていたようなので記憶に新しい。 「確かレンズがどうとかの話……だったよね」 「よく憶えてますねー。その通りですよ。過去に飛んだり未来に飛んだり」 「過去や、未来……」 「そうです……。そして、裏切りと孤独」 「…………」 「でも、魔法とか剣とかモンスターとかが普通にある世界ですよ」 ファンタジーで浪漫がありますよね。 そう言う悠の横顔にこっそりと苦笑する。 にしてみれば、たまに一家揃って消えたかと思えば、何処で売っているのか思わず聞きたくなるような奇怪なお土産を持って帰ってくる遥那家も十分ファンタジーの域に入る。本人達に言ったことはないが。 そんなことを考えているうちに辿り着いた分かれ道で立ち止まる。 のこれから向かう本屋の方角と、悠が歩いていく方角はどうやら違うようだった。悠の行く手に彼の家はないはずだが、それでは一体何の用があるのだろうか。 そう思いながらも聞かずにいると、悠が口を開いた。 「僕はこっちに用があるんです。それじゃ、また」 「うん、また」 手を振り別れ、別の道を歩き出そうとした瞬間。 の視界に、道路を曲がってきたトラックが映った。 「っ!」 悠の焦った声が耳を打つ。スローモーションのように見えるのかと何処か他人事のように考えているうちに、トラックはすぐ目の前にまで迫ってきていた。 スローモーションに見えるってのは、嘘だったのかな。 そう思ったの身体を、蒼い光が包み込んだ。 お願い、彼女を救って。 僕を救ってくれたから。 彼女を死なせないで。 運命の輪でいいから。 その中に避難させて。 そしてできれば。 …………彼も、救って。 その願い、受け入れましょう。 けれど、彼女がここに戻ってこられるか。 そこで生き抜いていけるかは彼女次第。 そして、彼を救えるかも。 私はただ、少し力を貸すだけ。 運命は、ヒトの手により創られるモノだから。 |
||
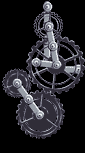 |
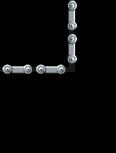 |